※本記事は2024年11月21日に投稿されたブログ記事『やりたい事を言葉にする』をリライトしたものです。
『察する』前に、子どもに言葉のチャンスを。
こんにちは。習志野市谷津のかるがも整骨院🦆です。
今日は子どもとの関わりの中で、私たちが大切にしている『言葉にする力』についてのお話です。整骨院に来てくれるお子さんたちと遊びながら話をするなかで、私たちは『察しすぎない』ことを意識しています。
島田家で禁止されている『三語』
島田家では日常会話で『あれ・それ・これ』という指示語の使用を禁止しています。
『それ取って〜。』と言われても、わかっていても『どれのこと?』と聞き返すようにしています。
なぜなら、大人が先回りして察しすぎることで、子どもが自分の気持ちや目的を言葉にするチャンスを失ってしまうからです。
子どもが言葉にする前に、つい動いていませんか?
整骨院で子どもたちと関わっていると、こんなやりとりをよく見かけます。
- 『○○くんがこんなことしてきた!』(→どうしてほしい?)
- 『僕、のどかわいた〜。』(→何がしたいの?)
- (ゴミを手に持って黙って差し出してくる)(→どうしてほしい?)
普段からお子さんの様子をしっかり見ているからこそ、困っていそうな場面で先回りして手を差し伸べてあげる…。そんな習慣がついている親御さんも多いと思います。
助けたい気持ちを少し我慢する勇気
でも、そこをちょっとだけ待ってあげてほしいです。
『どうしてほしいのか。」『何をしたいのか。』を
自分で言葉にするチャンスを子どもにあげてほしいのです。
うまく伝えられなくても大丈夫。それが言語表現の第一歩です。
“助けすぎ”が当たり前になると…
もちろん、大人が手伝えば物事はスムーズに進みます。
でも、助けられることが当たり前になってしまうことで
『自分で決めて、行動する。』ことが難しくなっていきます。
困ったときに誰かがなんとかしてくれる…。
そんな風に思ってしまうのは、本人のせいではなく、
助けすぎてしまった大人の関わり方かもしれません。
コミュニケーションは日常の積み重ね
生活のほんの一場面でも、こうしたやりとりが言葉の習慣になります。
『ちょっと助けすぎていたかも…。』
そんな視点を持っていただけたら、私たちとしてもとても嬉しいです。
📢 ご予約・お問い合わせはこちらから
ご予約の際は「希望日・時間帯」をご記載ください。
かるがも整骨院🦆|千葉県習志野市谷津5-27-15 三山マンション102

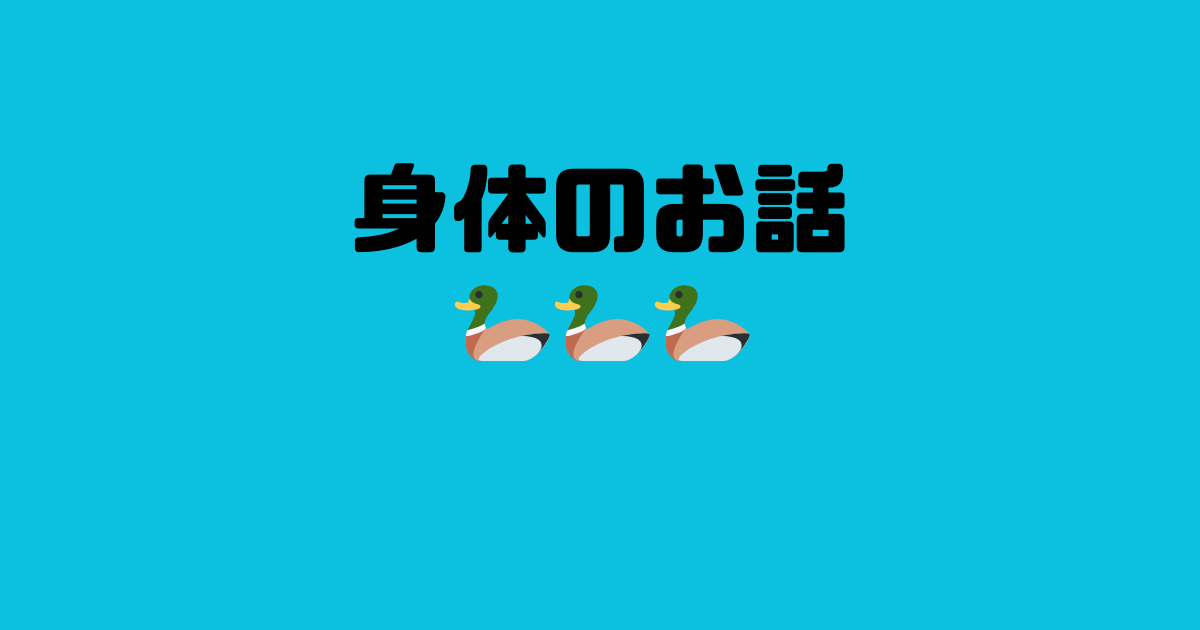


コメント