こんにちは。習志野市谷津のかるがも整骨院🦆です。
今日は、サッカーやバスケなどの競技で使われる『靴』についてのお話です。
最近は、スポーツ用の道具も驚くほど進化しています。
靴もどんどん軽く、グリップ力が強く、見た目もかっこよくなっている一方で、
それを使う“体の準備”が追いついていないケースが増えているように感じます。
◆ 道具に頼りすぎるリスク
お子さんの年齢が上がるにつれ、競技の専門性が高まり、スパイクや競技特化型のシューズを使う機会も増えていきます。
ただ現代の子どもたちは十分な外遊びや基礎運動の機会が少ない傾向があり『走る・跳ぶ・転がる・止まる』など、発育段階で自然に獲得すべき動作が身についていないまま競技を続けていることも少なくありません。
その結果、道具の性能に『助けてもらって』止まれているという状態が発生します。
実際のところは『自分の体の力では止まれていない』ということが起きているんです。
では、その未完成な『止まる』動作の負担を受けているのはどこでしょうか?
他でもない『子どもたちの体』です。
◆ 島田家長男もスパイクはまだ早いという考え
我が家も例に漏れず、サッカーをしている長男にも当てはまる話です。学年が上がりまわりの子がスパイクを履き始める中、島田家はしばらくスパイクを履かせない方針を取っています。
理由は単純で『まだ体が道具(スパイク)に耐えられる段階ではない』と判断しているからです。
◆ 道具を選ぶのは親の視点と判断
習い事や部活動を続ける中で、道具と縁を切ることはできません。
だからこそ、私たち親が考えなければならないのは、
『その道具は、今のうちの子にとって本当に必要か?』
『その道具を使える“体”が今できているのか?』
見た目や価格ではなく『お子さんがちゃんと道具を使えるか』という視点が大切だと思います。
◆ サインは体から届く
もし、道具を変えたあとに痛みを訴えたり、動きに違和感が出てきたら──
それは体からのサインかもしれません。
その道具を使うための体の準備が、まだ整っていない可能性が非常に高いです。
◆ 道具の前に遊びの土台を
大人と同じく、子どもにも“過剰性能の道具”は必要ありません。
まずは体を自由に動かす、外で遊ぶ、いろんな動きを経験する。
そうした土台ができてはじめて、道具の力を活かせるようになります。
一見地味ですが、そうした積み重ねこそが、怪我を防ぎ、長く楽しく競技を続けるための鍵なんです。
\ ご予約・ご相談はこちらから /
かるがも整骨院では、以下の方法でお問い合わせいただけます。
ご都合に合わせて、お気軽にご連絡ください。
- ✅ LINE予約:
 かるがも整骨院 | LINE Official Accountかるがも整骨院's LINE official account profile page. Add them as a friend for the latest news.
かるがも整骨院 | LINE Official Accountかるがも整骨院's LINE official account profile page. Add them as a friend for the latest news. - ✅ Instagram:
@karugamo.f - ✅ お問い合わせフォーム:
ホームページの専用フォームからも受付中です。 - ✅ お電話:
047-770-0113
皆様からのお問合せお待ちしております♪
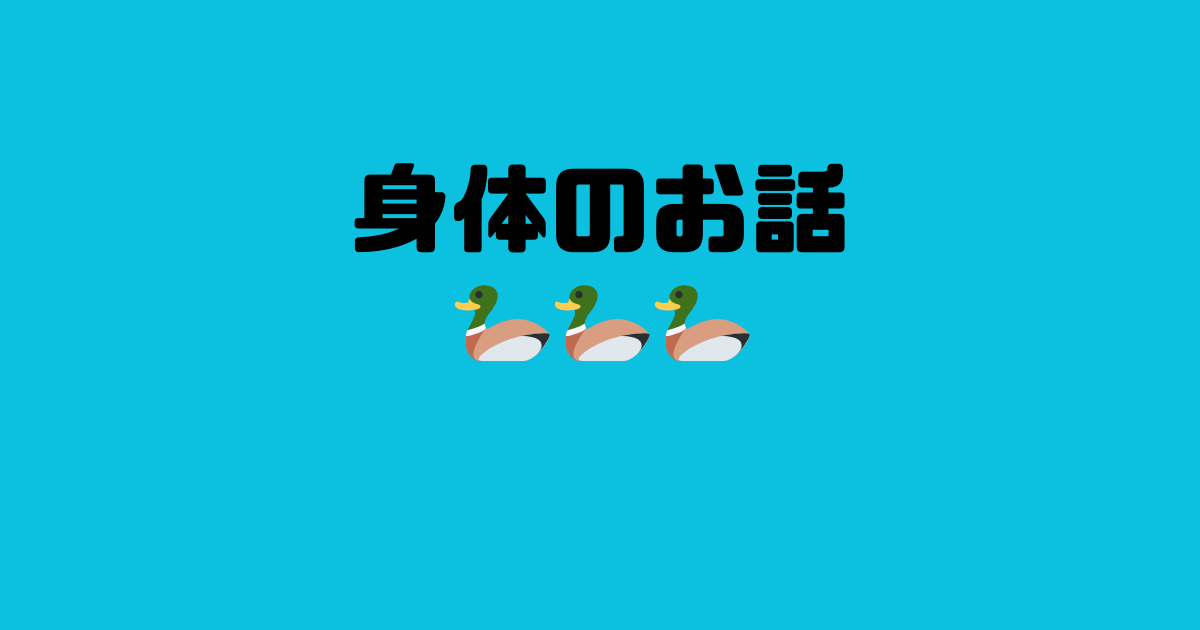

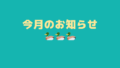

コメント